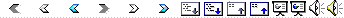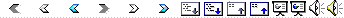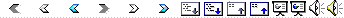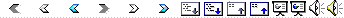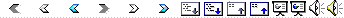|
1
|
|
|
2
|
- ���ꂩ��̓��{���ǂ��Ȃ邩�A�@�����ȃV�i���I�����B
- �@�����Ƃ��āA�ȒP�Ȑ����̃}�N���o�ϕ���
|
|
3
|
- �@���{�@�@��@�@�p���@�@�h�C�c�@�@�t�����X
- �@34.4�@ �@16.1 �@�@15.6 �@�@23.3 �@�@�@20.9
- �@27.2 �@�@18.0 �@�@16.3 �@�@21.0 �@�@�@21.8
- �@���ŕ\���@��i�͂P�X�X�P�N�@���i�͂P�X�X�X�N
- �@�f�[�^�̏o���Ȃǂ͘_���Q��
|
|
4
|
- �@���S�ٗp�S�O�O���~�̃P�[�X
- �@�i���~���Q�O���Ƒz��j
- �@���������~���~�������~
- �@�S�O�O���~�~�O�D�Q�@���W�O���~�˔���c��
- �@��Ƃ��S�O���~�w���{���{���R�O���~
- �˂P�O���~������c��
- �ː��Y�k�����f�c�o�����{���Ƒ���
- �˃}�C�i�X�����{�f�t��
|
|
5
|
- ���������R�T�O���~�̃P�[�X
- ���������~���~�������~
- �@�R�T�O���~�~�O�D�Q�@���V�O���~�˔���c��
- �@��Ƃ��S�O���~�w���{���{���R�O���~
- �ˎ����ύt�A���������Ɨ��T�D�T��
|
|
6
|
- ���x�����I���Ȍ�A���{�͍������~���̂��߉ߏ�����o�ςɂȂ��āA�s������ԂƂȂ��Ă���
- �@�Q�l�F�n���b�h�E�h�[�}�[�������_
- �@�@������v�����������{���Y���~���~��
- ���{���}�N���o�ϓI���v�s���������Ԏ��ŕ���Ă���
|
|
7
|
|
|
8
|
- ��P���Ζ��V���b�N�`�o�u���j�����O�i�P�X�W�V�N�j�̊���
- �@�@���{�������Ԏ��Ŏ��v�s�����U
- �@�@���{�̍����Ԏ���U�̋K��
- �@�@�@�@�@�@GDP�̂S������V�����x
- �@�@�˓����̃f�t���M���b�v�̑傫��������
|
|
9
|
- ���̊Ԃ̖��ڌo�ϐ������i���j
- �@2.0�@2.6�@1.0�@-1.1�@-0.2�@�@0�@�@1.0
- �ː��{����GDP��P�O���O��̍����Ԏ��ŁA���v�s�������Ă��A�܂��A���v�s��
- �˂��̊��Ԃ̓��{�o�ς̃}�N���o�ϓI���v�s���͂P�O���ȏォ�H
|
|
10
|
- ������P�O�����x�̎��v�s����������
- ���{�̍����Ԏ���U���K�v
- �������D�D�D
|
|
11
|
- �@1975�N�@�@23���~
- �@1980�N�@�@95���~
- �@1985�N�@164���~
- �@1990�N�@217���~
- �@1995�N�@323���~
- �@2000�N�@548���~
- �@�Q�O�O�Q�N 9��������
- �@���y�юؓ������ݍ���631.5���~�A���{�ۏ؍����ݍ���58.7���~�ŁA���v��690���~
|
|
12
|
- ���{�o�ς̐i�H�F�����ȃV�i���I
- (a)��
- (b)���E�E�|�Y�Eΰ�ڽ�E�\��
- (c)���C���t��
|
|
13
|
- (�)���N����P�O�N�ȏ�̕s����
- �@�o�ς����������V�Y�Ɣ������o�ϊg��
- �@�����ɕK�v�ȋ���V�Y�Ƃ����邩�H
- (�)���N����P�O�N�ȏ�̕s���Ŋ��������s�A�s������
- �@�@���Ɨ��R�O��/GDP������(b)��(c)�ֈڍs
|
|
14
|
- (�)�o�ς��h������A�i�C�������I������������������������Ŏ��������ݐϐԎ�����
- �@�V�������F�i�C�������I���������q���㏸���������x��������(1000���~��5���Ȃ�50���~)
- �@�Q�l�F���[���b�p�̌��݂̗��q���S�`�T��
|
|
15
|
- (�)�قڌ���̂܂܁A�ݐϐԎ��i����690���~�j�������A���Ƃ��A10�N��ݐϐԎ���1200���~
- ��̫��(�������錾)��\�z�����w����������̫�ā����Ԏ��Y��ʂɏ��Ł����E�E�|�Y�Eΰ�ڽ�E�\��
- ���ԋ��Z���Y����(���o�֎~)��100�����Y�ۗL�Ł����E�E�|�Y�Eΰ�ڽ�E�\��
- ���Ɨ��R�O��/GDP���������E�E�|�Y�Eΰ�ڽ�E�\��
- (�)(�)�ǂ�����(c)�ֈڍs
|
|
16
|
- �����s����ɂȂ��āA���⌔���s�ō����x�o���n�C�p�[�C���t��
- �n�C�p�[�C���t���ō��̗ݐϐԎ���肪����
- �n�C�p�[�C���t����100���߂����Y�ۗL��
- ���N���x�ŁA�ُk�����ŃC���t������
- ���̌�̓��{�o�ς́H
|
|
17
|
- �p���t���ȃ��[�_�[���o�ꂵ�A�S�̎�`�I�ɂȂ��ėL���Ȑ�������{����
|
|
18
|
- ����Ҏ��Y�� �Љ�ۏ�̍����ɂ��ė�����
- �@���ʇ@������㏸�����~���ቺ
- �@�@�ˉߏ�����o�ϖ�肪����
- �@���ʇA�ݐύ����Ԏ�������
- �@�@���݂̍���ҋ��Z���Y�͖�R�O�O���~
- �@�@�c��̐��オ�����͂V�O�O���~���H
- �@�@�@�@�{����҂̎����Ɣ䗦�͖�X�O��
- �@���ʇB��N�J���҂ւ̉ߓx�ȕ��S�Ȃ��Љ�ۏ����
|
|
19
|
- �s�Ǎ���肪�����Ă��錴��
- �i��j�n�������ŁA���{��S�z����ł��Ȃ�
- �iہj���������ŁA���Z�@�ւ̗̑͒ቺ
- �iʁj�؋����Ă����Ƃ̗�����������
|
|
20
|
|
|
21
|
|
|
22
|
- �N�x�@��Ɛ��@���Y�@ �s�NJ�Ɛ��@�s�Ǎ��z�@�䗦
-
�i���~�j
�@�@�@ �i���~�j
�i%�j
- �P�X�X�U�@ 2418�@338.7�@�@�@ 602�@�@�@�@101.9�@ �@30.0
- �P�X�X�V�@ 2410�@331.1 �@ 506�@ �@ 88.5�@�@ �@26.7
- �P�X�X�W�@ 2408�@329.3 �@ 629�@ �@ 98.0�@�@ �@29.8
- �P�X�X�X�@ 2165�@310.8 �@ 745�@ �@ 114.2�@�@ �@36.7
|
|
23
|
|
|
24
|
|
|
25
|
- �������͖����O�D�P�Q���ቺ
- ���̂܂܂̐����Ői�߂�
- �@�Q�O�O�O�N�x�ɕ��ςQ�D�X���������������́A
- �@�P�O�N��ɂ͂P�D�V��
- �@�Q�O�N��ɂ͂O�D�T��
- �@�Q�T�N��Ƀ[�����ȉ�
|
|
26
|
- ���{��Ƃ̗������͐����I�ɒቺ���Ă���Ƃ����������A�����̓��{��Ƃ��s�Ǎ��ƌ��Ȃ����ő�̌���
- ���{�o�ς̌i�C�����A�������ቺ�X�����t�]���A���{��Ƃ̏����ɑ��Ė��邢�\�z�𗧂Ă邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��A������������B��̕��@
|
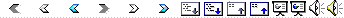
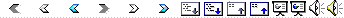
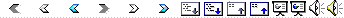
 �m�[�g
�m�[�g